多くのゴルファーにとって、「ユーティリティアイアン」は、思ったほどの助けにはならない存在だ。使用率が最も低いクラブのひとつとされるのも、それなりの理由がある。
「ハイブリッド」やロフト角の大きいフェアウェイウッド(#7や#9など)に比べて打ちこなすのが難しく、「寛容性」に乏しい。置き換えるはずのロングアイアンよりも扱いにくいと感じる場面すらある。
そんな中でPING「iCrossover」の“魅力”は、他とは一線を画していた。
ユーティリティアイアンが苦手なゴルファーにとっては驚くほど使いやすく、さらに「競技志向者(上級者)」にとっても「本当に優れた1本」と言える完成度を備えていた。
この“二面性の魅力”が評価され、MyGolfSpyの性能テストではたびたび総合1位に輝き、常に高い評価を集めてきた。
データで示すのは難しいが、このモデルはユーティリティアイアンというジャンルの敷居を下げ、アベレージゴルファーから「競技志向者(上級者)」まで、幅広いゴルファーにとっての現実的な選択肢へと進化させた。

ただし、「iCrossover」にはひとつ課題もあった。それは“ブランドとしての立ち位置”だ。
初代モデルの登場時、PINGは一貫してこう強調していた──「これはドライビングアイアンではない」と。
その狙いは明確で、従来のドライビングアイアンよりも幅広い用途に対応できるクラブとしてアピールすることだった。
だが、その「誰にでも合うクラブ」という打ち出し方が、逆に“ドライビングアイアンを求めるゴルファー”の候補から外れてしまった可能性もある。そして登場したのが「iDi」だ。
ここでPINGは“再定義”に踏み切った。しかもその意図は、ネーミングからはっきりと伝わってくる。PING流に言えば(略して“PINGO”とでも呼ぶべきか)、この名前には明確な意味が込められている。
「i」は「競技志向者(上級者)向け」の「iシリーズ」を指し、「Di」はドライビングアイアンの略。
つまり、「iDi」はPINGが公式に“ドライビングアイアン”として位置づけたユーティリティアイアンということになる。とはいえ、従来の「iCrossover」が持っていた万能性や使いやすさは、ほぼすべて受け継がれている。
本当に優れた進化というのは、物事を“あるがまま”に呼ぶことから始まるのかもしれない。
ただし「iDi」の物語は、単なる名称変更だけで終わる話ではない。そこには、もっと多くの進化が詰まっている。

「iDi」の進化ポイント
まず目を引くのは、見た目の変化だ。
PINGは今回、ブレード長(ヒールからトウまでの長さ)を5%短縮。構えたときに、よりコンパクトに見えるようデザインされている。
この変更は、ツアープレーヤーやPINGのテストチームからのフィードバックによるもの。
「見た目は小ぶりに、でも構えたときに安心感が持てる存在感は残してほしい」という要望に応える形で形状が見直された。
ブレード長の短縮は、見た目だけの変化ではない。
PINGはソール幅も広げ、バウンス設計も見直している。これにより、ハイブリッドに近い形状が生まれ、地面との接触を抑えつつ、インパクトではスムーズに抜け、しっかりと打ち込める構造に仕上がっている。
さらに、セット全体でライ角を1〜1.5度ほどフラットに変更。
これにより、特に大きく左へ引っかけるミスを防ぎ、左右のブレを抑えたストレートで安定した弾道を実現している。
中でも注目すべきは、フェースの高さに関する設計変更だ。
PINGは今回、フェースの高さを抑えたことで、より薄いフェース構造を可能にしている。これはユーティリティ/ドライビングアイアンとしては、PING史上最も薄い設計だ。
さらに、「鍛造C300マレージング鋼フェース」との組み合わせにより、「ボール初速」と「飛距離性能」がこれまで以上に向上している。

3つのテクノロジーが連携
今回の「iDi」で最も革新的な進化といえるのが、『inR-Air(インアール・エア)』と呼ばれる新構造だ。
これは、キャビティのカバーを装着する前に内部へ組み込まれる空気入りのパックで、イメージとしてはNIKEのスニーカーに使われている“エアバッグ”のようなもの。
ただし、その目的はまったく異なる。PINGはこの構造によって、中空構造のメタルウッド型アイアンで課題となる振動と打音の問題を解決しようとしている。
この『inR-Air』は、これまでPINGが使用してきた『EVAポリマー』に代わる構造だ。
フェースとヘッド内部の形状の両方に接する形で配置され、インパクト時の不要な振動を抑える役割を果たす。同時に、「マレージング鋼フェース」の効果を最大限に引き出す“高いフェースのたわみ”も維持できるよう設計されている。

『inR-Air』と連携するもうひとつの構造が、『iBEAM(アイビーム)』だ。
これは、バックフランジ(後方部分)とトップレール(上部)をつなぐように一体成型された補強構造で、ヘッド内部に組み込まれている。
この“ビーム構造”が加わることで、打音や打感はさらに洗練される。
PINGによれば、打感は「芯を感じる落ち着いた感触」で、精密なアイアンを求めるゴルファーが期待するような、心地よいインパクトを生み出しているという。
3つ目の要素が「カバー付きキャビティ構造」だ。
これは、ABS樹脂製のパーツをメッキ加工し、クラブ全体のデザインに自然になじむよう仕上げたもの。
一般的にプラスチック素材はネガティブに捉えられがちだが、ABS樹脂はスチールの約7分の1という非常に軽い素材。
この軽量構造によって余剰重量を生み出し、それをヘッド下部へ再配置することで、パフォーマンス向上につなげている。

番手ごとに最適化された性能
「iDi」には、2番(17°)、3番(20°)、4番(23°)の3つのロフト角がラインナップされている。
ただし、PINGは単にロフト角を変えただけでなく、それぞれの番手に明確な役割を持たせている。
なかでも2番アイアンは、“ドライビングアイアン”としての役割が明確だ。従来の18度から17度へロフトを立て、低弾道・低スピンの強い球を打てる仕様にチューニング。
ティーショットでの「飛距離」と「操作性」を重視した設計となっている。
3番アイアンはロフト角20度のままで、飛距離と打ち出しの高さのバランスを重視。
一方で4番アイアンは、ロフト角を0.5度寝かせて23度に設定。高さとコントロール性能を引き出し、グリーンを狙うアプローチショットでの使いやすさを意識した仕様となっている。
もし「iDiの中で、ひとつだけ“ドライビングアイアン”と呼べないとすれば?」という問いがあるなら。それは間違いなく4番だろう。
また、すべての番手でシャフト長が短くなっており、特に2番アイアンは3/8インチカットされている。これは、「iDi」から通常のアイアンセットへスムーズにつながる、自然で一体感のある流れを生み出すための工夫だ。

フィッティングとカスタマイズ
「iDi」では、『可変スリーブ』を搭載していた「iCrossover」とは異なり、あえて『固定ホーゼル設計』へと戻している。
この変更により、「競技志向者(上級者)」が求めるロフト角やライ角の微調整には十分対応しつつ、フィッティングをよりシンプルに行えるようになった。
シャフトは標準で「2.0 Chrome」を装着。さらに、「iDi」の性能を最大限に引き出すべく、新たに「2.0 Black 90」もラインナップされている。
このシャフトはもともと「G440」向けに開発された低打ち出し・重量タイプで、今回は特にヘッドスピードが速いゴルファー向けに調整されている。

性能について
「iDi」の性能向上は“劇的”ではないが、“確かな進化”がある。
PINGによれば、すべてのロフトでわずかではあるものの確実に「ボール初速」が向上しており、短くコンパクトになったヘッド形状が、最高初速を維持しながらショットごとの安定性も高めているという。
方向性に関しても、テストでは全体のバラつきが約11%改善されたというデータが出ている。
左右どちらへのミスも減少し、特に“距離が足りずラインから外れるショット”を抑える効果が顕著だった。
ユーティリティアイアンを使うゴルファーが悩まされがちなミスを軽減できる点は、大きな進化と言えるだろう。
弾道に関しても、番手ごとに明確な違いが出るよう設計されている。
2番アイアンは、前作よりも明らかに低弾道で飛び、まさに“本格的なドライビングアイアン”としての役割を果たす仕様となっている。
3番アイアンは、従来と同じような打ち出しと弾道の高さをキープ。
一方で4番アイアンは、より高い頂点を描く弾道で飛び、アプローチクラブとしての役割が強調されている。シャフト長が短くなったにもかかわらず、薄肉フェースによる「ボール初速」の向上と、重心位置の最適化によって「飛距離」はしっかり確保されている。
それでいて、「コントロール性能」はさらに高まり、扱いやすさも向上している。

ポジショニング戦略
「iDi」がとりわけ興味深いのは、PINGがこのクラブをユーティリティカテゴリーの中でどのように位置づけているかという点だ。
フェアウェイウッドやハイブリッドの“代わり”ではなく、特定の状況で最適な選択肢。特に風の影響を受けやすい場面や、飛距離をしっかりコントロールしたい場面で力を発揮するクラブとして提案されている。
「普段使いのクラブとは別に、状況に応じて使えるクラブをもう1本バッグに忍ばせておく」。
そんな考え方に共感するゴルファーなら、「iDi」が非常に頼れる選択肢になる理由はすぐにわかるはずだ。
フラットフェース設計により、弾道の高さを自分でコントロールしやすく、打ち出しの高いハイブリッドなどと比べても、操作性は段違い。
特に、風に向かって打つ場面や、狭いフェアウェイでの正確なティーショットなど、“飛距離と方向の両立”が求められる状況では、フェアウェイウッドやハイブリッドには出せない強みを発揮する。

まとめ
「iDi」は、“まったく新しいクラブ”というよりも、PINGが「成功したレシピ」をさらに磨き上げた1本だ。
「iCrossover」で高く評価された「高弾道」「しっかり止まる性能」「扱いやすさ」はそのまま継承。
そこにさらなる洗練が加わり、今作では従来のユーティリティユーザーだけでなく、“ドライビングアイアン派”のゴルファーにとっても魅力ある選択肢となっている。
すでに「iCrossover」を使っているゴルファーにとって、「iDi」は馴染みのある打感や操作性を残しつつ、性能面では確かな進化を感じられるはずだ。
そして、これまでドライビングアイアンを探してきたゴルファーにとっても、「iDi」は非常に魅力的な選択肢となる。
クロスオーバーならではの扱いやすさに加え、低弾道と高いコントロール性という、まさに求めていた性能を備えている。

PING「iDi」の詳細はPINGホームページまで。
発売は2025年9月4日。
※下記はアメリカ仕様の情報。
PING「iDi」は、7月17日より発売開始予定。フィッティング用クラブは7月8日から店頭に並ぶ。メーカー希望小売価格は295ドルだが、実売価格はそれよりやや安くなる見込み。



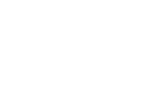



Leave a Comment