ベスページ・ブラックでの『ライダーカップ』を前に、ファンの期待は高まるばかり。
そんな中、ショットスコープの“データオタク”たちはひとつの遊びに興じていた──ゴルフが強いのはアメリカか、ヨーロッパか?『ライダーカップ』といえば、ファンの熱狂が“善と悪”の両極を引き出す大会。
確かに“ゴルフという競技“を生んだのはヨーロッパだが、250ヤード先から「入れ!」と叫び、ゴルフカートをビール運搬車に変える“エンターテイメント”を完成させたのはアメリカ人だ。もし7,000人のアマチュアゴルファー、アメリカとヨーロッパから3,500人ずつを集めて対決させたら?
ショットスコープはそれを現実にした。
ハンディキャップ0から30まで、6段階のレベル別にゴルファーを揃え、“アマチュア版ライダーカップ”をデータで検証したのだ!(笑)
いよいよここに、栄えある『第一回アマチュアライダーカップ』が開幕する。ただし競技内容と結果はプロの舞台とはひと味違う。増えるのはガッツポーズではなく、3パットとロストボールの山。
第1ラウンド:平均飛距離

勝者:アメリカ(やっぱり飛ばし屋!)
まずはアメリカの見せ場。平均飛距離は246ヤードで、ヨーロッパの230ヤードを大きく引き離す結果となった。
その差16ヤード──これこそ、アメリカ人ゴルファーがスコア95でも妙に胸を張っていられる理由かもしれない。データはショットスコープの「パフォーマンス・アベレージ」に基づいており、外れ値は除外済み。
つまり、一度だけ飛んだ320ヤードの豪快ショットは残念ながらノーカウントだ。第2ラウンド:ショットの正確性

勝者:ヨーロッパ(なんてこった)
ここでヨーロッパが反撃開始。フェアウェイをとらえた割合は49%で、アメリカの48%をわずかに上回った。
たった1%差?いやいや、ゴルフの世界ではその1%が勝敗を分ける。
なにせ「今のパットは2フィート11インチ(約89cm)か、3フィート(約91cm)か」で延々と議論できる競技なのだから。第3ラウンド:ティーショットでのロストボール

勝者:ヨーロッパ(堅実だね)
ここはアメリカにとって手痛い数字。1ラウンドあたりのロストボールはヨーロッパが1.08個、アメリカは1.62個で、その差は0.54個。
数字だけ見れば小さいが、裏を返せば毎ラウンド約2ドル(約300円)分。二度と戻らない「Pro V1」の“お布施”を払わずに済む計算になる。第4ラウンド:パーオン率

勝者:アメリカ(巻き返した!)
ここでアメリカが反撃。平均パーオン数は1ラウンド6回(34%)と、ヨーロッパの5回(27%)をしっかり上回った。
やはり飛距離のアドバンテージは大きい。短いアイアンで狙えるかどうか、その差がスコアに表れることを証明した一幕だ。第5ラウンド:50ヤードからのピンまでの距離

結果:引き分け(どっちもどっち?)
50ヤードからのショット結果は、アメリカもヨーロッパも平均ピンまで33フィート(約10メートル)つまり互角。
これは両大陸がウェッジの極意を会得したのか、それとも“揃ってイマイチ”なのか。答えは読者に委ねよう。第6ラウンド:100ヤードからのピンまでの距離

勝者:ヨーロッパ(微差でも勝利!)
ここはヨーロッパがわずかにリード。平均ピンまでの距離は51フィート(約15.5メートル)で、アメリカの54フィート(約16.5メートル)より約1メートル近かった。
数字だけ見れば大差ではないが、“3フィート縮めた”という事実は大きい。どうやらヨーロッパ勢のほうが、あの扱いづらい中途半端なウェッジ距離を少しうまくさばけるようだ。第7ラウンド:寄せワン率

勝者:ヨーロッパ(ショートゲームの妙)
ここもヨーロッパが優勢。寄せワン成功率は33%と、アメリカの30%を上回った。
両チームともグリーンを外す場面が多い中、このショートゲーム力こそが“ボギーで踏みとどまれるか、ダボに転ぶか”を分けるカギとなる。第8ラウンド:バンカーセーブ率

勝者:アメリカ(砂場で勝利!)
ここはアメリカが紙一重の勝利。セーブ率18%で、ヨーロッパの17%をわずかに上回った。
実質どちらも“砂遊びは運次第”だが、アメリカとしては「ビーチバレー以外でも砂で勝てる」と胸を張れる結果になった。第9ラウンド:3パット回避率

勝者:アメリカ(ちょっと進歩!)
ここではアメリカが僅差でリード。1ラウンド平均の3パット数は2.38回で、ヨーロッパの2.42回をわずかに下回った。
つまりアメリカ勢のほうが、ほんの少しだけ“グリーン上で発狂せずに済んでいる”ということ。わずかでも進歩は進歩だ!第10ラウンド:ショートパット成功率

勝者:ヨーロッパ(決め切った!)
ここはヨーロッパが3%の上積みで勝利。ショートパット成功率は54%と、アメリカの51%を上回った。
マッチプレーではほんのわずかな差が流れを決める。この3%こそ、勝者が笑顔で握手するのか、敗者がパターを池に投げるのか…その分岐点になるのだ。第11ラウンド:1ラウンドあたりのバーディ数

勝者:アメリカ(ついにバーディ!)
ここはアメリカがリード。1ラウンドあたりのバーディ数は0.9で、ヨーロッパの0.7を上回った。
派手さこそないが、“1ラウンドで1つもバーディが出ないこともある”現実を考えれば、この0.1の差が勝敗を左右する価値ある一打になる。第12ラウンド:ダブルボギー以上

勝者:ヨーロッパ(大叩きを回避!)
締めくくりはヨーロッパに軍配。平均すると1ラウンドで“大叩き”は3.38回、アメリカは4.13回と明確な差が出た。
つまりヨーロッパ勢の方が、「なんでこんなバカげたゲームを始めたんだ」と嘆きたくなるような壊滅的スコアを避ける術に長けている、というわけだ。最終結果

ショットスコープが行った12カテゴリーのデータ対決は、6.5対5.5でヨーロッパの勝利。アマチュア版ライダーカップも、最後は薄氷の決着となった。
もちろんアメリカ人としては言わせてもらいたい。
「この数字、どこか怪しい。“自由”と“ホットドッグ摂取量”といった“マッチョな強さ”は計算に入ってないだろ?」と。結末は実際のライダーカップ同様、ぎりぎりまで分からなかった。──これは『ベスページ・ブラック』でも再び大接戦を予感させるのか。
それとも単に、アメリカもヨーロッパも“スコア80を切れないための工夫”においては同じレベルだという証明なのかもしれない。マッチプレーで勝敗を分けるのは、フェアウェイをキープし、グリーンをとらえ、膝が震えるようなショートパットを沈められるかどうか。
その勝負どころでは、ヨーロッパにやや分があった。 ただしアメリカも負けてはいない。圧倒的な飛距離と、3パットを避ける粘り強さで存在感を示した。データが語る勝敗の行方
ショットスコープのGPSウォッチやレーザー距離計を使っているなら、あなたのラウンドデータも今回の“世紀のデータ対決”に加わっていたかもしれない。
もしかして、あなたも勝ちチームの一員だった?では本番、2025年の『ライダーカップ』ベスページ・ブラックはどうなるか。
アマチュアですら互角の戦いを見せたのなら、週末は手に汗握るドラマが待っているはずだ。あとは願うだけ…ロストボールと3パットが、このアマチュア版より少ないことを。


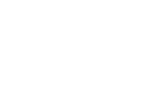



Leave a Comment