最近観たグラント・ホーヴァットのレッスン動画が妙に心に残っている。
チッピング(転がして寄せるランニングアプローチショット)をただの「構え方」「クラブ選び」「手の位置」といったチェック項目にとどめず、さらに一歩踏み込んでいたからだ。彼が焦点を当てたのは、ウェッジの中でも理解されにくい「バウンス」。この要素に目を向けることで、ショートゲームの見え方が一気に変わってくる。多くのアマチュアは「バウンス=バンカー用」と思い込んでいるが、実際にはグリーン周りでの「寛容性」を支える鍵となる部分だ。
うまく使いこなせれば、たとえ完璧でないチップショットでも十分に勝負できる結果を生み出してくれる。基本のセットアップがすべての土台
「バウンス」を活かす前に、まずは基本を正しく身につける必要がある。
・体重配分は前足に7割 ─ リード足にしっかり乗せることで、インパクトの最下点がブレにくくなる。その体重はアドレスで決め、スイング中も変えないこと。
・スタンスはコンパクトに ─ 足幅を狭くするだけで、動きはずっとシンプルになる。
・ボール位置は中央に ─ 右に置きすぎず、かといって左に寄せすぎない。これらのチェックポイントを守れば、鋭いリーディングエッジだけでなく、ウェッジの「ソール」を活かすことができる。
こうした基本を押さえることで、リーディングエッジではなく「ソール」を正しく使えるようになり、ウェッジ本来の性能を引き出せる。バウンスを無視すると待っている落とし穴
多くのアマチュアがやりがちな動きがある。手を前に突き出し、ボールを極端に右足寄りに置き、結果としてリーディングエッジで芝を突き刺す──その瞬間から「トップしてグリーンを駆け抜ける」「ダフってショート」といった致命的なミスが顔を出す。
つまり、ウェッジの「リーディングエッジ」だけで地面をとらえている限り、ミスを避けて通る余地はほとんど残されていない、ということだ。

バウンスを味方につける実践ステップ
ウェッジの「ソール」を地面に対して上手く使えば、クラブは突き刺さらずに“スッと滑る”。
これこそ「バウンス」が果たす役割だ。芝をえぐるのではなく、サッとなでるような感覚が伝わってくるはずだ。実際にホーヴァットは動画の中で、わざとボールの手前に接地させながらも、しっかりプレーできるショットになることを見せている。これは「リーディングエッジ」が地面に刺さるのとは違い、「バウンス」が滑ってくれるから起こる。
「バウンス」を生かすポイントは、手元をほんの少し前に置くこと。出しすぎてしまうとロフトが立ちすぎて、かえって「バウンス」が働かなくなる。
ところが多くのアマチュアは、構えの段階で手をボールより大きく前に押し出してしまい、その結果「バウンス」を活かせない打ち方になっているのだ。
ステップ4|なぜ「バウンス」はショットの寛容性を高めるのか
「バウンス」はいわばショットの保険。ミスを帳消しにしてくれる余白のような役割を果たす。
多少ダフっても、逆に少し手前で入っても、クラブは地面を突き刺さずに滑りながらボールをグリーンに届けてくれるのだ。「バウンス」がなければ、チップショットは一打たりとも誤差を許さないシビアなものになる。
だが、この“クッション”があるからこそ、パーを救えるか、それとも余計な一打を重ねるか──その分かれ道を左右するのだ。最後に伝えたいこと
ダフリやトップが止まらないとき、その解決策は必ずしも長時間の練習ではない。大切なのは、バウンスに仕事をさせることを覚えることだ。
「バウンス」はクラブの中で唯一、ミスを受け止めてくれる“寛容性の塊”。芝を突き刺すのではなく、軽くブラシのように地面をなでる感覚を確かめてみよう。そうすれば、プロがなぜバウンスを武器にしているのか、そしてアマチュアがなぜ無視できないのか、その理由がすぐに腑に落ちるはずだ。


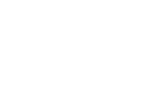



Leave a Comment