スコッティ・キャメロンが新作を「ラインエクステンション(拡張)」として打ち出した──そう聞いて、思わずニヤリとした。
表向きには、「11R OC」と「Fastback OC(ファストバックOC)」は、それぞれ「Phantom(ファントム)」シリーズと「Studio Style(スタジオスタイル)」シリーズの流れを汲むモデル。
確かに、定義上は“拡張”にあたる。そこに嘘はない。
だが、キャメロンのことをよく知る人なら気づくはずだ。これは、そんな単純な「シリーズ拡張」ではない。
むしろ、“新章の幕開け”だ。
キャメロンがひそかに仕込んでいたのは、“ブランド初”となる『ゼロトルクパター』。この瞬間、スコッティ・キャメロンが“トルクウォーズ”という名の戦場に足を踏み入れた。
クラシックな感性と革新的なテクノロジー、その両輪でパターの歴史を動かしてきたキャメロンが、次に挑むのは「トルクゼロ」という未知の領域。
もはや「シリーズ拡張」などという言葉では、とても語りきれない。
スコッティ・キャメロン、トルク戦争への参戦 ─ 遅れてきた主役

スコッティ・キャメロンが「ゼロトルク」という新たな領域を市場へ送り出すまでには、長い時間を要した。ツアーではその片鱗はすでに見えていた。
たとえば、ゲーリー・ウッドランドのキャディーバッグに収まっていたあの試作モデル。キャメロンが何かを企んでいることは、ファンならとっくに気づいていたはずだ。それでも、ツアートラックの中で磨かれてきたその設計が、ようやく店頭に姿を現したのは今だ。
遅い? いや、キャメロンにとって“早さ”は価値ではない。同じ時間軸で見れば、オデッセイなど他ブランドはすでにゼロトルクデザインを量産し、「Square 2 Square(スクエア・トゥ・スクエア)」も第3世代に到達している。
だが、キャメロンは違う。流行を追わない。正解が見えるまで動かない。なぜここまで時間をかけたのか?理由はただ一つ。「本当に正しいゼロトルク」をつくるためだ。
数値や理論ではなく、打った瞬間の“感覚”で納得できるものを完成させる。それがスコッティ・キャメロンというブランドの流儀なのだ。
この1年、キャメロンはツアープレーヤーたちとともに、数多くのゼロトルク試作モデルをテストしてきた。
我々がツアー中継やSNSで目にした“試作品”は、ほんの氷山の一角にすぎない。
その裏で、姿を見せぬままテストと改良を重ねたモデルが、数え切れないほど存在する。「納得のいくゼロトルクを追求した」。一見すると曖昧な言葉にも聞こえるが、キャメロンというブランドを知る者なら、その意味は痛いほど理解できるはずだ。
キャメロンのパターには、形にも仕上げにも一貫した“品格”がある。ただ重心を調整してトルクを抑えるだけの設計では、キャメロンの名を冠する意味がない。
見た瞬間に“キャメロンらしい”と感じられなければ、発売する価値がないのだ。だからこそ時間をかけた。そしてその結晶が、ついに姿を現す。11月11日、新たな「OC」デザインが、店頭に並ぶ。
スコッティ・キャメロン、ついに“OC”へ ─ ゼロトルクパターの新時代

「OC(Onset Center、オンセットセンター)」という名前には、キャメロンらしい設計思想が込められている。
“Onset”は『フェース面よりわずかに後方』、“Center”は『ヘッドの重心中央』──つまり、『シャフトが重心軸上に通るゼロトルク設計』を意味している。ゼロトルクの発想自体は、いまや珍しいものではない。多くのメーカーが、シャフトを重心上に通すことでトルクを抑制している。
だが、キャメロンは“構造”の作り方からして違う。L.A.B. Golf や ベティナルディ(Bettinardi) がヘッドに直接シャフトを差し込むスタイルを採用しているのに対し、キャメロンは「スパッドホーゼル構造」を選んだ。
その理由はシンプルだ。打感と調整性を両立させるためである。ホーゼルを設けることで、ライ角やロフト角を細かく調整できる対応力を確保しながらも、トルク特性を損なわない。キャメロンのテストデータでは、標準の「1°フォワードプレス」から±1°の微調整を行っても、トルクバランス(ねじれ特性)に影響が出ないことが確認されている。
つまり、操作性とフィーリングを犠牲にせず、ゼロトルクを実現した設計。キャメロンが時間をかけて辿り着いた答えが、この「OC」構造なのだ。
⚙️補足「フォワードプレス」とは:アドレス時に手元をボールより前に出す動作や、その状態のこと。
「1°フォワードプレス」とは:標準仕様でフェース面が1°だけ前に倒れている(=シャフトが1°前傾している)設計を意味する。なぜ“1度”だけ前傾させるのか?そうすることで、
・打ち出しの安定性が増す
・ハンドファースト(手が先行する)構えを再現しやすい
・インパクト時のロフトが立ち、転がりが良くなる
といった効果が得られる。
ゼロトルクでも変わらない ─「OC」はまぎれもなく“スコッティ・キャメロン”

大局的に見れば、キャメロンのゼロトルク構想は、他ブランドのアプローチと大きく変わらない。
それも当然だ。トルクを打撃から排除する方法は、最終的には物理法則という共通の原理に行き着く。だが、キャメロンはそこに「キャメロンらしさ」を加えた。見た目の美しさ、打ったときの感触、ストローク中の一体感──そのすべてが“Scotty Cameron”であること。
そこに、彼らが最も多くの時間を費やした理由がある。ゼロトルクを追求するほど、一般的には“打感”が損なわれやすい。パターにおけるトルクとは、言い換えれば“生命線”のようなものだ。
それをすべて消してしまえば、プレーヤーはストローク中にヘッドの存在を感じにくくなり、クラブとの“対話”が失われてしまう。
キャメロンはそこを理解している。だから、ゼロトルクでありながらも──「打感を生かすゼロトルク」を追い求めた。
科学と感性、その境界線を突き詰める。それこそが、スコッティ・キャメロンというブランドの真髄なのだ。

ゼロトルクパターの世界では、クラブを“操る”のではなく、“信じて任せる”ことが求められる。
プレーヤーが余計な力を加えず、ヘッドの自然な動きを受け入れる。それがゼロトルクの本質であり、慣れるまでに少し時間がかかるのも無理はない。だが、キャメロンの「OC(オンセットセンター)」パターはそこが違う。振った瞬間に伝わってくるのは、どこかで覚えのあるキャメロン特有のフィーリング。
ゼロトルクの安定感を備えながらも、“パターを振っている”という確かな手応えが残る。もちろん、理想的なストロークは今も昔も変わらない──ヘッドに任せること。しかし「OC」では、そのヘッドの動きを目で追い、体で感じ取ることができる。
ストロークの中で、ヘッドがつま先を通り過ぎていく軌道までも見て感じることができるのだ。キャメロンが魅せる“美フェース” ─ 極上の打感を生む新ミルドパターン

2025年のパターで、筆者が最も心を奪われたのが、キャメロン「Studio Style」インサートの打感だ。
チェーンリンク状のミルドフェースとカーボンスチール──この組み合わせが生み出すインパクトは、柔らかく、それでいて芯のある感触。
打った瞬間、指先に“職人の手仕事”が伝わってくる。タイトリストの「Left Dash(Pro V1x Left Dash)」ゴルフボールをこのフェースで打った時のフィードバックは、まさに完璧。
ひと言でいえば、“シェフのキス”そのものだ。シリーズ拡張として登場した「Studio Style Fastback OC(スタジオスタイル ファストバック オンセットセンター)」には、既存の「Studio Style」シリーズと同じインサートが搭載されている。これはある意味、当然の流れだ。

だが、もう一方の「Phantom 11R OC(ファントム 11R OC)」には、思わぬ進化が隠されていた。──そう、チェーンリンクミルドパターンの採用である。
このパターンがインパクトのフィーリングを一段階やわらげ、従来の「Phantom」モデルとは異なる温度を生み出している。どちらのモデルにも共通するのは、ゼロトルクでありながらも“打感が生きている”こと。
多くのゼロトルクパターが無機質なフィードバック(打感)に陥る中、「OC」シリーズは手の中で確かに息づいている。キャメロンが守ったのは、単なる打感ではない。“キャメロンの打感”──そのDNAを、ゼロトルクの新時代にも引き継いだのだ。
では、この2本のOCモデルをもう少し深く見ていこう。
ゼロトルクでも崩れない美『Studio Style Fastback OC』が示すキャメロンの矜持

「Studio Style Fastback OC(スタジオスタイル ファストバック オンセットセンター)」の箱を開けた瞬間、思わず笑みがこぼれた。 てっきりゼロトルク化の第一弾は「Phantom」だと思っていた──
まさか「Fastback」までもがゼロトルク仕様で登場するとは、うれしい誤算。初対面のインパクトは強烈だった。その瞬間、再確認したのは一人の名前──オースティ・ローリンソンだ。
20年にわたり「オデッセイ」の開発をつかさどり、現在はスコッティ・キャメロンのパター開発を率いるこの男の発想力は、やはり常軌を逸している。
「Fastback」はもともと、重心がフェースよりかなり後方にある構造。理論上、フランジ(ソール後方)にシャフトを挿せばゼロトルクは簡単に達成できる。
だが、それでは“キャメロンの美学”が成り立たない。実際、ツアー用の試作機には、キャビティ中央の低い位置にアダプターを取り付け、そこからシャフトを立ち上げるタイプのゼロトルク仕様が存在した。
見た目のバランスを犠牲にすれば、トルクは確かに消える。しかし、それは“Art of Putting(パッティングという芸術)”の世界観を壊す行為でもあった。キャメロンは、データと感性の境界で答えを探すブランドだ。
「Fastback OC」は、ゼロトルクという理論を“美”として成立させた、まさにその到達点である。シャフト位置を上方へ ─ キャメロンが導き出したゼロトルクの答え

「シャフトを、もう少しトップエッジ寄りに接合したい──」
そんな発想から、オースティ・ローリンソン率いる開発チームは、キャビティとトップラインの間に90度の新構造を設けるという、前例のないアイデアにたどり着いた。その結果として生まれた「Fastback OC」の姿は、決して“伝統的”とは言い難い。
だが、バックフランジにシャフトを挿した従来のゼロトルク設計に比べれば、はるかにキャメロンの造形哲学に近い美しさと機能の共存を実現した形だ。
「Studio Style Fastback OC」は、単なる実験ではない。キャメロンがゼロトルクという新たな設計領域を、ブランドのデザインコードの中で完全に昇華させたモデルである。
中型マレットという枠の中に、トルクレス構造と“パッティングという芸術(Art of Putting”)の美学が、見事に共存している。






「Phantom 11R OC」 ─ ゼロトルクと“Phantomらしさ”を両立した完成形

「Phantom 11R OC」── ようやくこの名前を言葉にできる時が来た。
「Phantom 11R OC」は、まさに自分が期待していたゼロトルクパターだった。昨年は何度もキャメロンに連絡を取り、“ゲーリー・ウッドランド・パター”について詳しい情報を聞き出そうとした。そのたびに返ってきた答えは、「ツアープレーヤーが使用する試作パターは市販されていません」というけんもほろろな回答だった。
それでも、ゼロトルク仕様の「Phantom」がいずれ店頭に並ぶという確信があった。──だが、待った甲斐はあった。

新しい「Phantom 11R OC」は、単なる派生ではない。
既存の「11」をベースにしながら、重心設計と打感のバランスを磨き上げた完成度の高いゼロトルクマレットだ。“R”は「Rounded(ラウンド)」の意味。
フェースの縁からキャビティのラインまで、すべてが柔らかく整えられ、特に前方のエッジが滑らかにカーブを描く姿は美しい。
このわずかな丸みが、構えた瞬間にプレーヤーの意識を自然とセンターへと導く。
角ばったラインよりも、曲線の方が視覚的に安心感を与える。もちろん、キャメロンチームはそれを計算づくでやっている。「Fastback OC」と同様、この「11R OC」もPhantomシリーズの世界観を崩していない。
個性はありながらも、シリーズの中に完璧に溶け込む。奇抜さではなく、熟成と統一感こそがこのモデルの魅力だ。ゼロトルクという新技術を採用しながらも、“Phantomらしさ”を失わない──
もしかすると、これらのモデルは本当に“シリーズの拡張”なのかもしれない。









『OC』を転がして検証 ─ ゼロトルクが生む打感と安定性

ゼロトルクを愛用している身として言えるのは──この2本は、どちらをバッグに入れても即戦力になる。
特に「Phantom 11R OC」は、試打後ほぼ即決でエース候補入り。いまやバッグの定位置を譲る気配がない。
意外だったのは「Studio Style Fastback OC」だ。正直、ラウンド形状と垂直ラインの組み合わせは、自分の得意パターンではない。
だが、フェース前方のサイトラインだけに意識を置き、パターの自然な動きに任せてみると──驚くほど結果が良かった。
ターゲットの合わせやすさは「11R OC」が上。だが、「Fastback OC」の打感は格別だ。“打つ”というより、“吸いつくように転がす”感覚。
正直、そのフィーリングの心地よさに夢中になり、ボールの行方さえ二の次になってしまう。
すでにセンターシャフトのゼロトルクパターを使っている人なら、この2本の「OC」はすぐに手に馴染むだろう。
ただし、インパクトの瞬間も、ストローク中も、キャメロンらしい“存在感のある打感”をより強く感じるはずだ。スコッティ・キャメロン『OC(オンセットセンター)』─ これは“大事件”だ!

キャメロンは今回、“最高のカード”を静かに切ったのかもしれない。いわば、「スロープレイ」の天才だ。
ポーカー用語で言えば、“ナッツ(最強の手)”を持ちながら、あえて相手を泳がせる──そんな戦略だ。「ただのシリーズの拡張です」と言わんばかりに、何気なく出してきた「OC」シリーズ。
だが、キャメロンを長く見てきた者なら、その静けさの裏に潜む意味を感じ取っているはずだ。
これは、業界全体を揺らす“静かだが確かな衝撃”だ。パーティーの主役が、ついにプールに飛び込んだ。
水面は穏やかではいられない──その波は、確実に他のすべてのブランドへと広がっていくだろう。
スコッティ・キャメロンが、ついに“ゼロトルク”というテーブルに座った。その事実だけで、業界に一石が投じられたと言っていい。
しかもキャメロンは、単にトルクを消しただけではない。デザインも、打感も、まるでキャメロンそのもの。
ゼロトルク化による“失われた何か”が、一切ない。それを成し遂げたこと自体が、最大の驚きだ。希望小売価格は549ドル。「Phantom 11R OC」と「Studio Style Fastback OC」は、他ブランドのゼロトルクモデルと真正面から競う価格帯に位置する。
549ドル──確かに高い。だが、キャメロンにとって「高価格」はハードルではなく、ブランドの一部だ。
他社なら“勇気のいる価格”でも、キャメロンには“納得の価格”が成立している。結局のところ、重要なのは数値でも価格でもない。この2本が、ゼロトルクという新たな領域でも“キャメロンらしさ”を貫いているという事実だ。
彼がこの市場に少し遅れて現れた?──いいや、むしろ“満を持して”だ。
キャメロンがチップをテーブルの中央に差し出した瞬間、ゲームのルールそのものが変わる。新しい『Onset Center(OC)』パターの詳細は『ScottyCameron ホームページ』で確認できる。
キャメロンが描く“ゼロトルクの新境地”を、ぜひ自分の目で確かめてほしい。



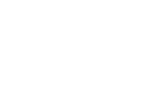



Leave a Comment