最新の飛び系アイアンのように市場の話題をさらうことはないかもしれない。
だが、ミズノが展開する「MPシグネチャーシリーズ」の第2弾となる「S-1」の登場は、ブランド自身の予想をも上回る成功を収めつつあるこのコンセプトを、さらに大きく広げるものとなっている。
今年(2025年)初めに「S-3」が登場したときから、これは“始まり”にすぎないことは明らかだった。
たった1モデルでは“シリーズ”とは呼べないし、販売実績がその可能性を物語っている。
実際、「S-3」は前作「JPX 923ツアー」と比べて販売数が83%も増加しており、ミズノにとって確かな成功を収めたモデルとなっている。

そして今回登場するのが「S-1」。一体鍛造のブレードアイアンで、「ミズノプロ241」の実質的な後継モデルにあたる。
「S-3」と同様に、これはシグネチャーシリーズに新たに加わるモデルであり、既存モデルの単なる置き換えではない。
「S-1」「S-3」といったネーミングの流れを見る限り、今後さらにラインアップが広がっていくことは十分に考えられる。
ミズノシグネチャーシリーズの理念
「MPシグネチャーシリーズ」の根本的なコンセプトは今も変わらない。
それは、近年ミズノが十分に応えきれていなかった「競技志向者(上級者)」や契約ツアープロに向けて、より幅広い選択肢を提供すること。
ミズノ「Sシリーズ」は、かつての「MPシリーズ」が持っていた魅力。クラシカルで時代に流されないデザイン、そして上級者や“本物志向”のゴルファーに向けたモデルづくりへの原点回帰でもある。
シグネチャーシリーズに共通するのは、どのモデルも“一体鍛造”であり、長く愛されることを前提にデザインされている点だ。
ミズノの名作アイアン「MP-33」「MP-37」「MP-60」、そして「MP-32」を思い出してほしい。
すでに市場からは姿を消したが、あの設計は今もなお色あせることがない“タイムレスな存在”として語り継がれている。
「S-1」もまた、この理念を受け継ぐモデルだ。
4年という長めの製品サイクル。長く使いたいという多くのゴルファーの声に応えるだけでなく、ミズノにとっても「ビジネスありき」ではなく、「ゴルファーにとって本当に必要なこと」を軸に判断できるようになる。

ミズノ「S-1」の登場
ミズノ「S-1」は、基本的には小ぶりなブレードアイアンだ。
全体としてオフセットは控えめだが、番手ごとに変化をつけた“段階的設計”が採用されている。
ロングアイアンではややオフセットを多めに、ショートアイアンに向かうにつれて徐々に少なくすることで、番手に応じた最適な構えやすさを実現。
また、トップラインはセットの中で少しずつ厚くなっており、ショートアイアンになるほど重心位置が高くなるよう設計されている。
これにより、風の影響を受けにくい伸びのある弾道と、グリーンで止まるスピン性能を両立できる。
全体的に見れば、「S-1」のブレード長は「ミズノプロ241」よりわずかに長くなっているが、それはほんのコンマ数ミリの差にすぎない。アドレス時にその違いに気づくことは、まずないだろう。
「ミズノプロ241」との大きな違いは、その輪郭にある。
「ミズノプロ241」はトウの丸みと全体のやわらかなラインが特徴的だったが、「S-1」ではトウの輪郭がやや角張り、直線的なラインが際立つデザインに仕上がっている。
これは現在のツアーで見られるトレンドを反映したもので、業界全体でもこうしたシャープな形状が支持を集めつつある。

個性を生む「チャンネルバック」構造
「S-1」のデザインに独自の存在感を与えているのが、バックフェースを横切るように設けられた“チャンネルバック”=溝状の構造だ。
この部分にあえて素材を使わないことで、そのぶんの重量をクラブ上部に再配分でき、縦方向の安定性が高まっている。
誤解してはいけない。「S-1」はやさしいクラブではないし、そのために作られたわけでもない。
ただし、この『チャンネル構造(溝状の構造)』によって、寛容性(MOI=慣性モーメント)はわずかに向上しており、それでもなお、「競技志向者(上級者)」が求めるピュアな打感と操作性はしっかりと保たれている。

環境への配慮という新たな価値
「S-1」には、もうひとつ注目すべきストーリーがある。それは、ミズノが進めている環境への配慮だ。
鍛造アイアンの製造では、どうしても多くの素材がムダになる。中でも「フラッシュ」と呼ばれる、金型からはみ出す余分な金属は、生産を重ねるほど大きなロスとなる。
「S-1」では、ホーゼル周辺のフラッシュを1本あたり43グラム削減。
一見わずかに思えるが、年間で約50トンの素材削減につながっており、廃棄物の削減という点でも大きな前進となっている。

打感へのこだわり
ミズノがこだわり続けてきた「打感」。その追求の一環として、「S-1」では打音解析ソフトを大幅に刷新したという。
これにより、ラボで得られるデータと、実際にゴルファーがコースで感じる打感とのギャップを、より正確に埋められるようになった。
新たなソフトでは単に“音の周波数”をシミュレーションするだけでなく、その音がどれだけ持続するか。
つまり“響きの長さ”まで把握できるようになり、サウンドと打感をよりプレーヤー好みに調整できるようになっている。

この改良は、PGAツアー選手のベン・グリフィンからのフィードバックが大きく影響している。変更点はあくまで繊細だが、すべてに意図がある。
ミズノのクリス・ヴォーシャルはこの打感について、「ややしっかりめのフィーリングで、これまでより少し“ボヤけた感覚”が抑えられている」と表現している。
とはいえ、打音が硬くなったり、カチッと不快に響いたりするわけではない。
「S-1」には従来どおりの銅下メッキも採用されており、あの“ミズノらしい”ソフトな打感は健在だ。
ただし今回のモデルでは、インパクト時の情報がほんの少しだけ“手に伝わる”ように設計されている。
スペックと展開について

ミズノ「S-1」の基本スペックは、他のシグネチャーシリーズのアイアンとほぼ共通。
ピッチングウェッジは46度、7番アイアンは34度で、3番アイアンの設定はなし。
また、製品ライフサイクルを4年と長めに設定していることで、右打ち用・左打ち用の両方を展開できるのも特徴だ。
サイクルが短ければコスト的に難しいが、この設計だからこそ両利き対応が可能になっている。
次なる展開へ
「S-1」の登場により、ミズノのシグネチャーシリーズは次のステージへと進んでいる。
すでにツアーでは、2026年9月の発売を視野に入れた新たなモデルのテストが始まっており、シリーズ全体の展開は着実に広がりを見せている。
この戦略は明らかに成果を上げている。
「競技志向者(上級者)」に向けて“本物の選択肢”を提供しつつ、クラシカルな外観と、名器たちが築き上げた打感・操作性といった性能の本質をしっかり守っているのだ。
「S-1」は、すべてのゴルファーに向けたアイアンではない。
これは、精度・打感・そして“良いスイングを正しく評価する”という設計思想を求めるプレーヤーのためのブレードアイアンだ。
やさしさや飛距離がもてはやされる今の市場において、ミズノがあえて“自分たちの強み”を貫く姿勢には、ある種の潔さと信頼感がある。

スペック・価格・発売情報
※下記はアメリカのスペック
「ミズノプロ S-1」の標準シャフトは「KBSツアー」、グリップは「Golf Pride ツアーベルベット」。価格は1本あたり215ドルとなっている。
詳細はミズノホームページをチェック。



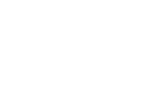



Leave a Comment